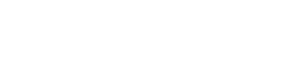激しくぶつかる辺野古基地建設問題をめぐって
本土と沖縄と米国 ―ワシントンは辺野古一辺倒ではない
基地負担は沖縄に対する差別
本年10月13日、沖縄県の翁長雄志知事が前知事による辺野古埋立の承認を取り消した。これに対し安倍政権は強硬姿勢を崩さず、工事再開に向けて即座に手続きを進めた。執行停止の申し立てを行い、承認取り消し処分が違法であるとして地方自治法に基づく代執行の手続きに入ると決定し、同月29日には埋立てに向けた本体工事に着手した。
沖縄では県民の79%が知事の承認取消を支持し(沖縄タイムス同月20日)、普天間基地の沖縄県内移設には実に83%が反対している(琉球新報2015年6月2日)。この世論調査の結果を待つまでもなく、沖縄は今「オール沖縄」で辺野古の新基地建設反対を訴えており、昨年の選挙では建設に反対する候補者が、辺野古の基地建設現場を抱える名護市長選、県知事選、衆議院選の総てで連続して勝利をおさめている。オール沖縄の代表である翁長知事は「あらゆる手段を使って辺野古の基地建設を阻止する。」と訴え続けている。
これまでも問題視されてきたものの、これまで以上に日本本土と沖縄の対立構造が明らかになり、沖縄では基地負担は本土から沖縄に対する差別であるとの評価が定着しつつある。
国務次官補候補にも名前があがる人物が辺野古案を疑問視
「いつまでたっても辺野古に基地はできないと思うよ」
9月上旬、ふとした立ち話の際、米国の友人が私にこのように言った。長年、米国政治の中心で日本を担当してきたその友人は、共に話に加わっていた日本の外務省の知人に向かって「あなたには申し訳ないけどね」と付け加えた。
翁長知事による埋め立て承認取り消しの後、米国務省は辺野古沖への普天間基地の移設について「米軍再編という構想を実現させるためには不可欠な措置」と述べ、沖縄の対応によっても日米の計画には変更がないとの認識を発表した。米国といえば、辺野古基地建設を頑なに推進する主体であるとの理解が日本国内では一般的であろう。確かに公式なレベルでの日米合意はこの間変わっていない。
しかし、ワシントンの内実はそれほど辺野古一辺倒でもない。上に発言を引用した友人は、国務次官補候補にも名前もあがる人物であるが、このように辺野古案を疑問視する意見や代替案の提示、また、別の案の検討を要するとする意見が頻繁に出されている。
その代表格は、2011年5月に、重鎮議員であるジョン・マケイン(現職)、カール・レビン(当時)、ジム・ウェブ(当時)氏ら3名の上院議員が出した声明である。「現在の再編計画は非現実的、実行不可能かつ財政的に負担困難」として、辺野古案の再検討を求めるものであった。そして米議会は実際に普天間基地からグアムに海兵隊を移転する予算を凍結し、この予算凍結が辺野古移設を間接的に困難にさせたともいわれている。
アーミテージも「代替案が検討されなければならない」
また、日本の外交・安全保障政策にもっとも大きな影響力を有すると日本で広く理解されているリチャード・アーミテージ元国務副長官も「代替案が検討されねばならない」と2010年頃から公の場で述べていた。
同様に強い影響力を持つとされるジョセフ・ナイ元米国防次官補も辺野古については長期的には解決策にならず、中国の弾道ミサイルの射程内にある沖縄に米軍基地が集中する現状を変えるべきであると指摘している。なお、ナイ氏は、「沖縄の人々が辺野古への移設を支持するなら私も支持するが、支持しないなら我々は再考しなければならない。」とすら述べている。
なお、本年、米議会にて、グアム選出の議員が、米国の軍事予算を決定する国防権限法(2016年度)の中に普天間基地の移設先は「辺野古が唯一の選択肢である」との文言を挿入しようと試みた。しかし、沖縄関係者のロビーイングの成果もあり、最終的には両院協議会のすり合わせにより同条文は削除されるに至った。
このように、ワシントンには、普天間基地の移設について様々な意見が存在する。日本本土の専門家の間では辺野古が唯一の選択肢であるという見解が大半を占めるのに比べて、米国の方がずっと柔軟な印象である。
在沖海兵隊の軍事的意義
「軍事的には沖縄でなくても良いが、政治的に考えると沖縄が最適の地域である」とは、森本敏元防衛大臣(現防衛相政策参与)のあまりにも有名な言葉である(2012年12月25日防衛大臣会見)。即ち軍事的には米海兵隊は沖縄におかなくても問題はないということである。
実際、辺野古への基地建設を求める論者からは「抑止力」を理由に米海兵隊の沖縄駐留が必要と説明されるが、現在、抑止の一番の対象とされる中国との関係を考えれば、米軍の軍事アセットを沖縄にここまで集中させることが逆に抑止力を脆弱化させかねない。アメリカの軍事政策のリアリズムにおいても、沖縄に現在の規模の海兵隊が駐留しなくてもよいと多くの論者が唱えている。例えば、米国防総省との関係が深いとされる米シンクタンクのランド研究所は、2013年、大部にわたる研究報告書を発表し、在沖海兵隊の一部を米国本土に戻しても緊急時の対応に大きな影響は生じないとした。
日本では米海兵隊の沖縄駐留がなければ尖閣諸島が中国に奪われるかのような見解もよく耳にする。しかし、新日米ガイドラインの下、島嶼防衛は日本に一義的な責任があるとされており、米海兵隊が一刻を争って尖閣諸島に駆けつけるという場面は想定されていない。また、尖閣諸島をめぐる日中の争いに米軍が軍事力で介入することは考えにくいが、仮にそのような事態があったとしても、米軍が空と海から敵を一掃するのみで地上戦闘部隊を島に上陸させる必要はない(元在沖海兵隊第3海兵遠征軍司令官ジョン・ウィスラー中将(現米海兵隊総軍司令官)・星条旗新聞2014年4月11日)。
実際に、沖縄に駐留しているとされている海兵隊は他地域での訓練などで沖縄を空けており、年に半年以上沖縄にいない。登記上の住所が沖縄にあるだけで実態がそこにあるわけではないのが現実である。
米海兵隊の沖縄駐留の必要性について議論を詰めていくと、皆、最後は「今、撤退すると中国に間違ったメッセージを送る。」という答えに行きつく。しかし、そのような印象論の問題であるのなら、日本政府が外交において手を打つ方法は辺野古基地建設以外にさまざまあるだろう。日米合意変更を可能とするための印象を含めた環境醸成のヒントは、上記ジョセフ・ナイ氏の意見等、既に提供されている。
日本政府の姿勢の転換を
日米において様々な可能性が提案されているにもかかわらず、日本政府の立場は一貫して辺野古基地建設推進である。
しかし、これほどまでに強い反対の意志をもつ沖縄を前に工事を物理的に強行すれば、沖縄県内の対本土感情はさらに悪化する。また、既に存在する米軍基地への憎しみもさらに増し、新基地ができたとしても沖縄での米軍基地のオペレーションを容易ならざるものにする可能性が高い。県内の首長や議員は口をそろえて「それなら普天間にとどまらず、嘉手納も、となる」と、米国が最重要視する嘉手納空軍基地に対して全県的な反対運動が飛び火することを示唆する。生活に直接の影響を受ける沖縄県民の民意への配慮は、今後の日米関係の安定のためにも重要である。
日本政府は、軍事的に他の選択肢が存在する現実において、沖縄におけるこの決定的な反対と真摯に向き合わねばならない。辺野古案が浮上して来年で20年である。この沖縄の反対は、「政治的にも」他の選択肢が困難であるのと同じかそれ以上に困難な選択肢であることを認めるべき時期に来ている。
直ちに日本政府が方針を転換するのは困難かもしれない。まずは工事を停止し、その上で、政府内部で日米合意の変更の方向を模索するプロジェクトチームを組織し、政治的、また、軍事・外交的な検討を綿密に行う。その上で、米国に辺野古での新基地建設は不可能である旨の意思を伝えるべきである。米国国内の基地保有自治体は、保有する基地の縮小や閉鎖に対して地元経済の観点から反対の意を唱えているが、そのような地の現状調査を行い、普天間の米海兵隊の受け入れの可能性を検討する点もプロジェクトの中で行われるべきである。
私はこの議論の度いつも元米政府の高官であり沖縄返還の米側交渉担当者であったモートン・ハルペリン氏から聞いた言葉を思い出す。沖縄返還交渉の際、米国政府の意思を忖度してものを言わない日本政府の担当者に対して、氏は、「沖縄を返してほしいならちゃんとそう言ってください。」と伝えたとのことであった。
まずは、辺野古での基地建設が不可能であることを日本政府が認識すること、そして、それを米国政府に適切な方法でしっかりと伝えることが必要である。
民主主義における選択とは
米国からの日本に対する直接間接の圧力があり、それが政府レベルでも民間レベルでも存在することは承知している。しかし、ワシントンにおける対日政策にかかわる人々の柔軟な姿勢に鑑みれば、日本が決意を固め、計画的にことを進めれば、辺野古の基地建設の合意の変更は可能であると筆者は考える。即ち、筆者は、辺野古の基地建設は日本政府の意思で強行されようとしている、と考えている。
沖縄の民意には見向きもしない日本政府だが、しかし、それは日本本土の人々の意思に照らしても正しい選択といえるのであろうか。あまり知られていないが、全国紙の世論調査でも産経新聞によるものも含めてその多くが辺野古基地建設を「評価しない」とする者が「評価する」とする者を上回っている(琉球新報2015年5月4日)。そして、日本本土においてこの問題が次のような意味をもつ問題であるとの認識が広まれば本土の反対はさらに高まるだろう。
そもそもこの問題は今後の日本の安全保障体制をどのように形作るか、米国とどのように良好な関係を保っていくのかといった国にとっての重要な事項についての判断である。それに加えて見落とされがちなのが、この問題が一つの地方自治体に決定的に大きな影響を及ぼす事態について国政がその自治体の意見をどう取り扱うのか、という意味をもつという点である。
現在の「沖縄のことは沖縄が決める」との沖縄の訴えは、事と時を違えば他の地域に当てはまる。そして、この地方自治と国との関係の問題において、今回の辺野古の基地建設における国の判断は今後の国政の中での大きな先例となっていく。沖縄の基地問題には本土の関心がなかなか集まらないが、自らにも跳ね返ってくる問題であると本土の我々が認識する必要がある。繰り返すが、地元である沖縄では8割が強く辺野古基地建設に反対なのである。
多くの点においてこれほど国の在り方に影響を及ぼす判断については民意がもっと反映されるべきであろう。この民主主義の要請に対し、時に、「外交・防衛は国の専権事項である上、米国との合意があるために変えられない」という説明がなされるが、軍事的・政治的に他の選択肢がある現状ではその可能性の中から民主主義的な選択を行うのが民主主義国におけるあるべき政府のすがたである。