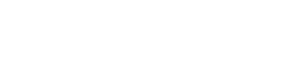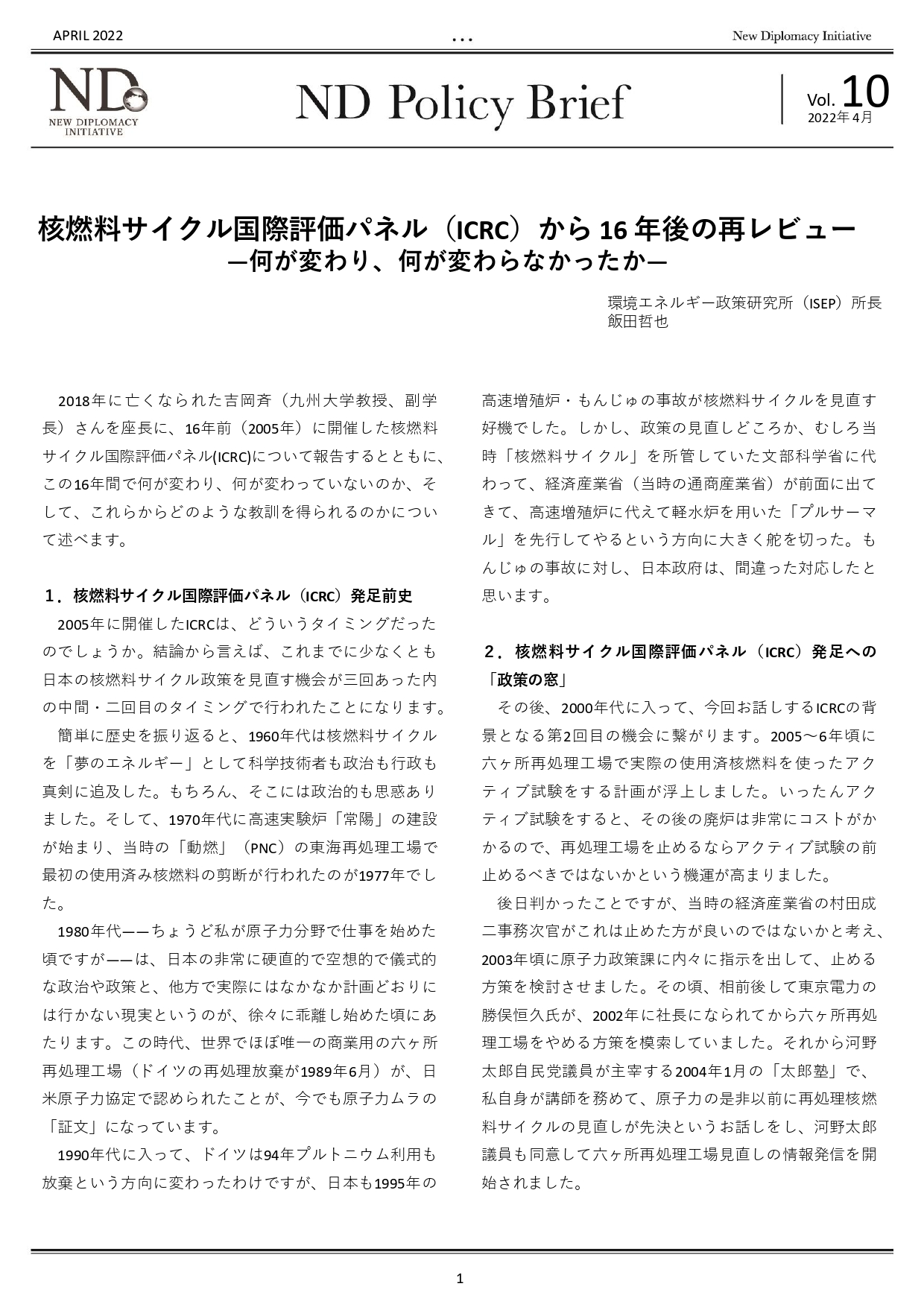環境エネルギー政策究所(ISEP)所長 飯田哲也
2018年に亡くなられた吉岡斉(九州大学教授、副学長)さんを座長に、16年前(2005年)に開催した核燃料サイクル国際評価パネル(ICRC)について報告するとともに、この16年間で何が変わり、何が変わっていないのか、そして、これらからどのような教訓を得られるのかについて述べます。
1.核燃料サイクル国際評価パネル(ICRC)発足前史
2005年に開催したICRCは、どういうタイミングだったのでしょうか。結論から言えば、これまでに少なくとも日本の核燃料サイクル政策を見直す機会が三回あった内の中間・二回目のタイミングで行われたことになります。
簡単に歴史を振り返ると、1960年代は核燃料サイクルを「夢のエネルギー」として科学技術者も政治も行政も真剣に追及した。もちろん、そこには政治的も思惑ありました。そして、1970年代に高速実験炉「常陽」の建設が始まり、当時の「動燃」(PNC)の東海再処理工場で最初の使用済み核燃料の剪断が行われたのが1977年でした。
1980年代――ちょうど私が原子力分野で仕事を始めた頃ですが――は、日本の非常に硬直的で空想的で儀式的な政治や政策と、他方で実際にはなかなか計画どおりには行かない現実というのが、徐々に乖離し始めた頃にあたります。この時代、世界でほぼ唯一の商業用の六ヶ所再処理工場(ドイツの再処理放棄が1989年6月)が、日米原子力協定で認められたことが、今でも原子力ムラの「証文」になっています。
1990年代に入って、ドイツは94年プルトニウム利用も放棄という方向に変わったわけですが、日本も1995年の高速増殖炉・もんじゅの事故が核燃料サイクルを見直す好機でした。しかし、政策の見直しどころか、むしろ当時「核燃料サイクル」を所管していた文部科学省に代わって、経済産業省(当時の通商産業省)が前面に出てきて、高速増殖炉に代えて軽水炉を用いた「プルサーマル」を先行してやるという方向に大きく舵を切った。もんじゅの事故に対し、日本政府は、間違った対応したと思います。
2.核燃料サイクル国際評価パネル(ICRC)発足への「政策の窓」
その後、2000年代に入って、今回お話しするICRCの背景となる第2回目の機会に繋がります。2005~6年頃に六ヶ所再処理工場で実際の使用済核燃料を使ったアクティブ試験をする計画が浮上しました。いったんアクティブ試験をすると、その後の廃炉は非常にコストがかかるので、再処理工場を止めるならアクティブ試験の前止めるべきではないかという機運が高まりました。
後日判かったことですが、当時の経済産業省の村田成二事務次官がこれは止めた方が良いのではないかと考え、2003年頃に原子力政策課に内々に指示を出して、止める方策を検討させました。その頃、相前後して東京電力の勝俣恒久氏が、2002年に社長になられてから六ヶ所再処理工場をやめる方策を模索していました。それから河野太郎自民党議員が主宰する2004年1月の「太郎塾」で、私自身が講師を務めて、原子力の是非以前に再処理核燃料サイクルの見直しが先決というお話しをし、河野太郎議員も同意して六ヶ所再処理工場見直しの情報発信を開始されました。
2004年初頭に、こうした三つの流れが合流し盛り上がり、いわゆる「政治と政策の窓」(ポリシーウィンドウ)が大きく開いて、核燃料サイクル見直しの気運が高まったのですが、結果的には見直されませんでした。同年6月に原子力委員会の下で原子力新計画策定会議が始まり、そこは推進派で固められて、全量再処理継続の流れで議論が進められました。翌2005年10月には「原子力政策大綱(新計画)」が取りまとめられました。
この「原子力政策大綱(新計画)」を国際的なレビューに掛ける趣旨で、吉岡斉先生と私とが高木基金をベースに動いたのがこのタイミングでした。もう一つ福島県の佐藤栄佐久知事(当時)も、この核燃料サイクルとプルサーマルは考え直すべきだという事で当時活動しておられ、佐藤知事、吉岡斉先生、飯田は密接に連携しました。
そして第3回目の見直しの機会は、福島原発事故でした。この事故によって政治的にも政策的にもカタストロフが起き、この時が核燃料サイクルを見直す最大のチャンスでしたが、ある意味ボタンの掛け違いで見直しができなかった。これについては後述します。
3.六ヶ所再処理工場を巡る経産省と東京電力のすれ違い
先ほどお話ししたとおり、政策見直しの機会は「六ヶ所再処理工場が汚染する前」の2004年に始まりました。ちょうど原子力政策大綱を見直すというタイミングにも重なっていたことと、それから経済産業省と東京電力、それらが若干バラバラですけれども、見直そうとの機運があった、そして河野太郎自民党議員も再処理について異議を呈しておられた。2005年のICRCは、そういう時期に実施されたわけです。
一方、経済産業省では、2004年6月の人事で退任予定の村田成二次官が、退任直前に当時の原子力政策課長の安井正也氏をいったん異動させました。安井氏が、原子力政策課の中で村田次官の意に反して、核燃料サイクルを進めるよう東京電力の見直し働きかけを止め、逆に推進側に舵を切ったからです。ところが、後任の柳瀬唯夫課長、後に森友問題や加計学園問題で有名になる方ですが、彼が原子力政策課の中で再処理を止めようとして動いていた課員の犯人捜しをし、全員を排除・異動させたことにより、経産省の「六カ所再処理工場」に対する反乱はそこで終わりました。舞台は原子力委員会の政策大綱の見直しの場に移りましたが、そこは推進派が最初から多数派なので「反乱」が起きるはずもありません。
一方で、六ケ所村の核燃料サイクル施設を運営する日本原燃は赤字続きで財務的に行き詰まっていたことから、電力会社からの再処理委託費を引き落とす口実が必要でした。最終的には2006年3月27日に佐賀県の当時の古川知事がプルサーマルを了解したという、その4日後の3月31日にアクティブ試験を始めるために、再処理施設内に保管されていた使用済核燃料を構内移動させただけで数百億円の「再処理役務費」を引き落とし、2005年度決算を黒字にしたわけです。3月31日という財政年度の切り替わる最終日に日本原燃の売上げを立てて黒字にするという、ほとんど粉飾決算かイカサマのようなことが行われました。
4.核燃料サイクル国際評価パネル(ICRC)の概要
ICRC報告の内容に詳細に入る時間はありませんが、簡単にご紹介します。当時の「原子力政策大綱(新計画)」では、核燃料サイクルについて、全量再処理を続ける、直接処分と再処理の組み合わせ、直接処分、いったん立ち止まるモラトリアムの4つのシナリオについて10項目で政策評価し、結果として全量再処理を続けるのが最もメリットがあるという結論でした。ただし、今、振り返ってみても、かなり強引なこじつけのような議論でした。
そこで翌2005年に、国際的な評価レビューを行いました。高木基金を事務局にして、私も委員で事務局長、アメリカのフランク・フォン・ヒッペル教授、イギリスのフレッド・パーカー氏、ドイツのクリスチャン・キュッパー氏、マイケル・シュナイダー氏と、そして吉岡斉先生と、海度雄一弁護士、橘川武郎先生、藤村陽さんという委員構成でした。橘川先生は当時から比較的熱心な原子力推進側だったのですが、むしろ推進側の先生も入れようという吉岡斉先生のご推薦と紹介でした。先ほどの河野太郎代議士や福島県の佐藤栄佐久知事とも連携をしながら進めていきました。2004年の原子力委員会原子力政策大綱(新計画)策定会議場で委員だった吉岡先生が提案をされ、並行して高木基金の方でも準備をして2005年の春に準備会合、そのあと2005年秋に、かなり画期的だったのですが、東京都内で福島県主催のこの核燃料サイクルの国際シンポジウム、当時の政策大綱会議の委員だった筑波大学の元電中研の内山先生、佐藤栄佐久知事にも出席していただき、ディスカッションしました。そしてその同じ月に吉岡先生がその原子力委員会の場でも報告をされ、そして暮れには佐賀県の唐津市、あるいは青森県等でも説明会をやったのですが、その翌年の2006年の3月に、佐賀県がプルサーマルを了解、そしてそのままアクティブ試験になだれ込んだという経緯になりました。
ICRC報告の内容は、原子力政策大綱(新計画)の四つのシナリオに対して、若干の遅れはあったとは言え、日本の原子力政策文書に対する初の国際的かつ科学的な政策レビューが、ほぼリアルタイムで行われたことは画期的だったかと思います。たとえば、全量再処理が最初から完全に固定的に政策の選択肢として入っていることに関して、もっと現実的な政策の選択肢が提案されるべきだという事が指摘されました。また、再処理を止めると使用済燃料が溜まって、それによって原子力発電が止まり、、石炭火力発電所を大量に設置する必要が出るので、そのためにコストが非常にかかるという「政策転換コスト」は、およそ非現実的な想定でナンセンスであること、核拡散とか安全性、あるいは不確実リスクなどがほとんど軽視をされていること、モラトリアム等で提案をした政策の柔軟性は完全に無視をされていること、その上で再処理を続けることが最も様々な点でメリットがあるという評価は非常に独断的である、といった点が指摘されました。
ICRC報告は今でも高木基金のホームページにありますが、明らかに論理破綻し矛盾している点が直裁に指摘をされており、今後も日本の原子力政策に対しては、こうした公正で信頼できる独立委員会で再レビューすべきと提言されています。
5.核燃料サイクル国際評価パネル(ICRC)が示唆する今後への教訓
ただし残念ながら、ICRC提言とは全く逆に、現実政治的には反対方向に暴走してしまいました。柳瀬氏が原子力政策課長に座って、ちょうど政治的にも安倍晋三第一次政権となり、原子力立国計画など原子力推進にアクセルが踏まれました。東芝がウェスティングハウスを買収するといったのも、このあたりに起きて、結果としてそれは10年後に東芝がほとんど倒産にするようなことにもなりました。様々のことがほとんどブレーキの利かない形で進み、どんどん政策が劣化をしていったのが、丁度この後のタイミングでした。
福島原発事故後ですが、原子力発電は今現在9基の再稼働が認められる一方、特重設備等の整備など様々な要因で止まっているところもあり、昨年の原子力供給シェアは6、7%です。かつてのように原子力は「基幹電源」ではなくなってきていることと、日本中で国民の意識は圧倒的に原子力に対して忌避感、拒否感があります。
ただし残念ながら、かつての民主党政権の下での「失敗」がありました。本来、原子力政策の段階論としては、原子力をするしない以前に、やはり核燃料サイクル、再処理、プルトニウムからの決別を決める方を、より先決すべきでした。スウェーデンも、ドイツもそうでした。ところが日本はそちらの議論が十分に国民的になされる前に福島原発事故が起きてしまった。とにかく原発をゼロにしようというコンセンサスは少なくとも国民の中ではあるものの、核燃料サイクルの議論がほとんど置き去りになってしまいました。
それは政治家もその知識があまりないという事と、一方で青森県と六ヶ所村に対しては、かなり明らかに電力と原子力マフィアが裏で動いた確証があります。当時、イギリスの核燃料会社(BNFL)から再処理返還廃棄物を、イギリスから日本に戻すというアナウンスメントが行われ、それに対して六ヶ所から「もし政府が再処理を止めるのだったら核のゴミは受け取らない」という応答がなされ、そういうダブルバインドに民主党政権(当時)を追い込んでいったという事がはっきりしています。結果として民主党政権は、再処理を続けるしかないという方向になった中で、原発ゼロだけを決めてしまったので、今度は核拡散を懸念するアメリカから大丈夫かという声があがりました。つまり、政策変更の手順を違えてしまった訳です。当時、それは自民党も民主党政権も脱原発政策に関してやはりプロフェッショナルな方がほとんどいなかったので、中間貯蔵という現実的な解決策が理解されていなかった。そこは今振り返っても残念です。
6.脱核燃料サイクルのコンセンサスが最初の第一歩
今となっては、日本は脱核燃料サイクルと脱原発を同時にやるべきですが、では核燃料サイクルと原子力をどのように止めていくか。脱原子力の論理は相当詰まっているのですが、プルトニウムを、あるいは核燃料サイクルをどのように止めていくかという論理とコンセンサスが遅れているという感じがあります。そこは早く詰めるべきだろうと思います。
この間に、一方で再生可能エネルギーが一気に進んだため、代替エネルギーとしての核燃料サイクルは、もはや意味がなくなりました。あとは軍事目的を放棄するだけです。図1(注:PDF参照)は太陽光と風力のコスト推移です。太陽光がこの間に十分の一のコストに下がり、風力は十分の三、七割コストが下がり、今やこの二つが最も安いエネルギー源で凄まじい勢いで増えています。先日のCOP26でも、まだ原子力と言っている人たちもいますが、世界の研究機関が出している将来シナリオほとんどが、特に太陽光と風力による再エネ100%というシナリオに移行しています。
一方で、核燃料サイクルはますます現実性を失っています。最近の政府の文書等々を見ても、およそ現実性のない方向を提示しています。今でも16年前のICRCの指摘は非常に有効だと思いますが、その矛盾だとか間違いはますます拡大しているという事で、一刻も早く見直すべきでしょう。核燃料サイクルが完全に詭弁で続行されているので、改めて独立の立場から、土台から問い直す方法論をやるべきでしょう。ただし前回は、政治・政策の窓「ポリシーウィンドウ」から若干遅れてしまったことが教訓なので、早めに備えた方が良いですね。その政策見直しの機会が出てきたときに具体的にこうすべきだという事を早めに準備していく方がいいでしょう。
核燃料サイクルは今の日本の中で最もでたらめな政策体系になのですが、今や新型コロナへの対応にしろ、脱炭素にしろ、再エネにしろ、日本の政策はかなり質が劣化しているので、ここは体制とかプロセスとか、より深い部分から見直しをしないと立て直しは非常に困難かもしれません。
※本報告は2021年12月18・19日に開催された「英独米中韓日6ヵ国シンポジウム〈増えるプルトニウムと六ヶ所再処理工場―核燃料サイクルの現実と東アジアの安全保障―〉」に基づいています。内容と意見は報告者個人に属し、NDの公式見解を示すものではありません。
※この企画は一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト(abt)の2021年度助成金を受けています。