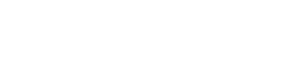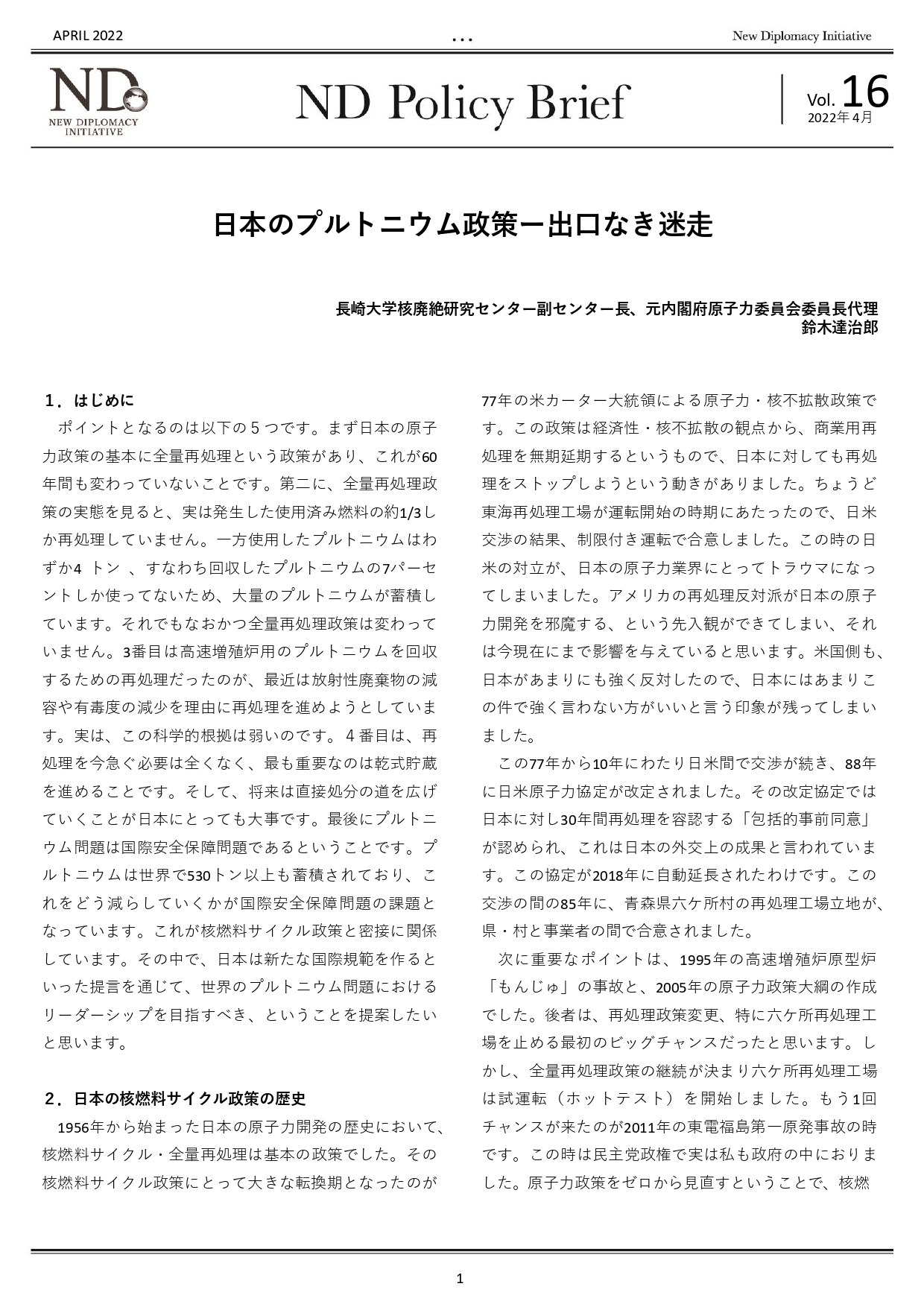長崎大学核廃絶研究センター副センター長、元内閣府原子力委員会委員長代理
鈴木達治郎
1.はじめに
ポイントとなるのは以下の5つです。まず日本の原子力政策の基本に全量再処理という政策があり、これが60年間も変わっていないことです。第二に、全量再処理政策の実態を見ると、実は発生した使用済み燃料の約1/3しか再処理していません。一方使用したプルトニウムはわずか4 トン 、すなわち回収したプルトニウムの7パーセントしか使ってないため、大量のプルトニウムが蓄積しています。それでもなおかつ全量再処理政策は変わっていません。3番目は高速増殖炉用のプルトニウムを回収するための再処理だったのが、最近は放射性廃棄物の減容や有毒度の減少を理由に再処理を進めようとしています。実は、この科学的根拠は弱いのです。4番目は、再処理を今急ぐ必要は全くなく、最も重要なのは乾式貯蔵を進めることです。そして、将来は直接処分の道を広げていくことが日本にとっても大事です。最後にプルトニウム問題は国際安全保障問題であるということです。プルトニウムは世界で530トン以上も蓄積されており、これをどう減らしていくかが国際安全保障問題の課題となっています。これが核燃料サイクル政策と密接に関係しています。その中で、日本は新たな国際規範を作るといった提言を通じて、世界のプルトニウム問題におけるリーダーシップを目指すべき、ということを提案したいと思います。
2.日本の核燃料サイクル政策の歴史
1956年から始まった日本の原子力開発の歴史において、核燃料サイクル・全量再処理は基本の政策でした。その核燃料サイクル政策にとって大きな転換期となったのが77年の米カーター大統領による原子力・核不拡散政策です。この政策は経済性・核不拡散の観点から、商業用再処理を無期延期するというもので、日本に対しても再処理をストップしようという動きがありました。ちょうど東海再処理工場が運転開始の時期にあたったので、日米交渉の結果、制限付き運転で合意しました。この時の日米の対立が、日本の原子力業界にとってトラウマになってしまいました。アメリカの再処理反対派が日本の原子力開発を邪魔する、という先入観ができてしまい、それは今現在にまで影響を与えていると思います。米国側も、日本があまりにも強く反対したので、日本にはあまりこの件で強く言わない方がいいと言う印象が残ってしまいました。
この77年から10年にわたり日米間で交渉が続き、88年に日米原子力協定が改定されました。その改定協定では日本に対し30年間再処理を容認する「包括的事前同意」が認められ、これは日本の外交上の成果と言われています。この協定が2018年に自動延長されたわけです。この交渉の間の85年に、青森県六ケ所村の再処理工場立地が、県・村と事業者の間で合意されました。
次に重要なポイントは、1995年の高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の事故と、2005年の原子力政策大綱の作成でした。後者は、再処理政策変更、特に六ケ所再処理工場を止める最初のビッグチャンスだったと思います。しかし、全量再処理政策の継続が決まり六ケ所再処理工場は試運転(ホットテスト)を開始しました。もう1回チャンスが来たのが2011年の東電福島第一原発事故の時です。この時は民主党政権で実は私も政府の中におりました。原子力政策をゼロから見直すということで、核燃料サイクル政策も見直しの議論をしました。しかし、その結果は全量再処理政策の堅持でした。現状、六ヶ所再処理工場は稼動していていないので、プルトニウム保有量は増えてはいませんが、さすがに2018年の原子力協定改定の時期が迫ると、米国から日本に対するプレッシャーがかかってきました。その結果、日本の原子力委員会が「プルトニウム在庫量を削減、これ以上増やさない」という政策を発表しました。これはエネルギー基本計画にも含まれ、閣議決定もされましたので、今後はかなりの強い制約が再処理にもかかるだろう、というふうに期待しております。
3.破綻した高速増殖炉の夢
高速増殖炉の夢が破綻したことを示すグラフをお見せします。図1(PDF版参照、以下、図表については同様)は70年代の米国の予測で、2010年に2500 ギガワットまで伸びるとされ、それに応じて高速増殖炉もかなり導入されるとみられていました。しかし、一番下にある黒い線(100ギガワット以下)が米国の現状です。原子力がこれだけ伸びれば高速増殖炉は必要だったかもしれませんが、実は現実はこんな低いところにとどまってしまった。世界も似たような傾向で、日本も1985年には、2030年までに100 ギガワット を目標とする計画でしたが、現実はそこまで行きませんでした。ウラン資源も枯渇するどころか、多くの鉱山がその後見つかりました。右の図は、天然ウランの価格と再処理価格の推移ですが、高速増殖炉が実現するには天然ウランの価格があがって、再処理価格が下がる必要があります。しかし現実はまったく逆で、天然ウランの価格は下がり、再処理価格は高騰した結果、再処理は経済性がないことが明らかになりました。
原子力委員会が出している原子力利用開発長期計画に書かれていた高速増殖炉の実用化目標時期を示したのが表1です。年を経るたびに高速増殖炉の実用化時期がどんどん遠のいて、最初は1970年代に実用化と言ってたのが、既に87年時には当面は軽水炉が主要電源と認めています。2000年になると将来の重要な選択肢の一つになってしまい、2006年の時には目標時期は示さなくなりました。そして2015年には21世紀後半となってしまいました。要するに高速増殖炉 はもう実用化の具体的目標がなくなってしまったということです。
経産省が使用している核燃料サイクルの図(図2)は軽水炉と高速増殖炉サイクルの両方が実現して、はじめてサイクルが成立するというものですが、最近軽水炉サイクルしか見せなくなりました。でも軽水炉だけですと、1回、せいぜい2回リサイクルしただけ終わってしまいます。したがって軽水炉サイクルでは、プルトニウム・ウラン混合燃料(MOX)の使用済み燃料は捨てるしかないのです。
ところが、日本では全量再処理政策のため、この使用済み燃料の直接処分が法律で認められていません。しかも2016年に再処理の法律が変わりまして、電力会社はすべての使用済み燃料の再処理費用をMOX燃料加工費も含めて、拠出する義務を負うことになりました。全量再処理の固定化といってもいいです。つまり再処理を優先した結果、どうしても余剰プルトニウムが出てくるという図でもあるわけです。
4.再処理の意義とリスクに対する疑問
表2は経産省が使用している核燃料サイクルの意義です。資源の有効利用も当然書かれていますが、最近は高レベル廃棄物の減容と、廃棄物の毒性の低下が示されています。図3は原子力委員会によるコスト評価の数値です。全量再処理のコストは直接処分の約2倍になります。それから2030年まで総額費用も比較していますが、直接処分は14兆円、再処理したら18兆円で4兆円の差があるとの結果が示されました。言い換えれば、大体年間2千億円ほど余計な費用が掛かるということになります。当時の、わりと保守的な見積もりでも年間2千億円も追加費用がかかるということです。
放射性廃棄物の減容についても調べましたが(図4)、高速増殖炉サイクルとワンス・スルーを比べれば確かに減るように見えます。ただし、軽水炉だけのリサイクルだと、MOX使用済み燃料を処分しなければいけません。MOX使用済み燃料の容積を加えると、ワンス・スルーと差はそれほどありません。さらに再処理から出てくる低レベル廃棄物の量を加えると、ワンス・スルーよりも容積は増えてしまうという結果が出ています。
図5は放射性廃棄物の有害度が下がっていくという、よく使われている図ですが、この有害度は実は危険性(リスク)ではない、と注がついています。普通この注までは見ないですが、あえてつけてもらいました。「廃棄物と人間との間の障壁が考慮されておらず」というところが重要で、「実は危険性ではない」と注できちんと書かれています。
これを分かりやすく説明したのが図6です。虎2匹と、虎1匹どっちが危ないかというと、虎二匹のほうが怖いです。ところが檻に入った虎2匹と野放しの虎1匹を比べると、野放しのほうが怖い。これが危険性(リスク)であって有害度(毒性)との違いです。再処理はこの閉じ込めてるものをわざわざ取り出して地上でぐるぐる回すわけですからリスクは高くなります。これがあの毒性とリスクの違いです。先ほどのグラフはこのトラが減っていく様子を見せているわけですが、檻に入っている危険なプルトニウムをわざわざ取り出してリサイクルするわけですから、当然リスクは高くなります。
これを実際の数値で見たのが表3です。これは経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)による核燃料サイクルからの被ばく量推定値ですが、再処理/リサイクルするとウランの需要が減るので、このウラン採掘からの被ばく量は減ります。したがって、ウラン鉱山からの被ばくは、ワンス・スルーのほうが高いです。ところが、再処理による被ばく量は高いので、合計の被ばく量を考えると、再処理/リサイクルの方が高くなっています。この表は原子力委員会小委員会で議論した結果、結論としてはあまり差はないということになりました。その議論が経産省の図には反映されていません。
5.第三者評価の重要性
なぜ再処理は止められないのか。その理由として、①使用済核燃料の行き先がない、②自治体との約束、③キャンセルを言い出した機関が、債務保証や自治体への謝罪等、責任を負わなければいけない、といった理由が挙げられます。この3番目の理由で、誰も自分から辞めるとは言えない状況になっています。確かに巨大な負債なので、これは大きなリスクになるということです。4番目は、安全保障問題に関係しています。再処理施設やプルトニウムを所有することが潜在的な核抑止力となるのでやめられないという意見もあります。私は5番目について、民主主義のシステムとして独立した評価機関がないという点に注目しています。日本にとっては、これが一番問題ではないでしょうか。再処理を止められないことで、結果的に犠牲者は国民と国際社会ということになります。民間でいくら評価をやってもなかなか政策決定に結びつかないという限界を私も感じてきました。国がこういう独立した第三者評価機関を持つということは非常に大事ではないかと思います。
6.使用済み燃料貯蔵のリスク
使用済み核燃料貯蔵のリスクですが、写真1の左が福島第一原発の4号炉です。ここで水素爆発を起こしてしまい、使用済み燃料貯蔵プールに水がなくなってしまったのではないかと当時心配しました。結果的には幸運にも水があったのですが、もし水がなくなってしまうと原子炉の事故と匹敵するぐらい、あるいはもっと悪い結果を及ぼす可能性がありました。安全なのは、写真右にあるキャスクに入れる乾式貯蔵です。福島第一原発の貯蔵施設の建屋は津波で壊れてしまいましたが、建屋内に置かれていたキャスクは安全でした。しかも空冷なので電気を使わないため、電源がなくても大丈夫です。したがって、今後は乾式貯蔵が安全な貯蔵方法だといえます。
7.プルトニウムと国際安全保障:日本政府への提案
図7は、世界のプルトニウム貯蔵量の推移です。軍事用のものは減少していますが、民生用がかなり増えているのがわかります。国別に見ると、核保有国でありますが民生用として英、ロシア、フランス、それに日本の四カ国でほとんど保有量の全部を占めています。今日話がありました中国はこれから民生用再処理を増やしていこうとしています。他のドイツとか過去再処理を行っていたが中止した国々は、今はほとんどプルトニウムを持っていません。したがって、この四カ国が再処理を止めれば民生用プルトニウムも減っていく可能性があるということです。
私は笹川平和財団の研究会で座長を務めさせていただいて、次のような提案を研究会として発表しました。それは、日本が新しいプルトニウム国際規範を作れるのではないか、というものです。提言には五つのポイントがあります。第一に、しばらく使う目途が立たないプルトニウムを「余剰」プルトニウムとして定義して、それを国際原子力機関(IAEA) の管理下に置く、という提案です。これにより、国際懸念はかなり解消されると思います。第二に、先ほども申しました日本の原子力委員会のプルトニウム利用の基本的考え方で示された「プルトニ
ウム在庫量を増やさない、今後減らしていく」という政策を新たに国際プルトニウム管理指針(INFCIRC/549)として提案する、というものです。その結果、再処理を抑制することができる、と考えられます。第三に、実際にプルトニウム処分における国際協力を促進するためのフォーラムを立ち上げる、という提案です。第四は、再処理よりも、使用済み燃料の乾式貯蔵をできるだけ優先することを提案しました。また、核燃料サイクルについて、独立した第三者機関の評価を行うことも提案しました。最後に日本がそのリーダーシップをとるという提案です。
※本報告は2021年12月18・19日に開催された「英独米中韓日6ヵ国シンポジウム〈増えるプルトニウムと六ヶ所再処理工場―核燃料サイクルの現実と東アジアの安全保障―〉」に基づいています。内容と意見は報告者個人に属し、NDの公式見解を示すものではありません。
※この企画は一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト(abt)の2021年度助成金を受けています。