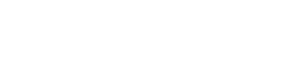明田川 融
法政大学教授
日米地位協定には改定が必要と考えられる問題点が数多くある。それを詳述する紙幅はないので、沖縄県、渉外知事会、全国知事会などの改定要請にゆずるが、近年、私が論評を求められた点だけでも、以下のものがある。①基地から/基地へは、米軍人等が出入するにもかかわらず、検疫に関する規定が存在しないこと(米側が、その責任で検疫を行なうとする内容の合同委員会合意はある)、②当初、日本政府が地位協定および関連取り決めでできないとしていた区域外訓練が行われており、同訓練に関する解釈も実弾射撃等を伴わない訓練は区域外で認められると変更されてきていること、③基地周辺住民の生活や安全に直接かかわる内容を協議しているにもかかわらず、その内容や合意の多くが秘密とされている日米合同員会のあり方と、同委員会に住民代表や自治体が加わることの是非。そして、米側が排他的に管理権を有するとされる基地への立ち入り、在日米軍に対する日本国法令の適用という課題がある。
◆比較の視座
米国は、第二次大戦中から、冷戦体制崩壊後の今日にいたるまで、世界に広がる「基地帝国」を構築してきた。そのため、米軍基地とそこに在る米軍人・軍属らを規律すべき取り決めについて何らかの洞察を得ようとする者にとっては、自国が米国と結んでいる取り決めと、他国と米国との間の取り決めを比較検討することが、一つの有効な視座を与える。
日本について言えば、そもそも日米地位協定の前身である行政協定締結交渉において、また、同協定改定交渉において外務省が範と仰いだのは、NATO軍地位協定(1951年)や旧西ドイツに駐留するNATO軍の地位に関する、いわゆるボン補足協定(1959年)であった。その後は、国会図書館調査立法考査局、地位協定研究会、本間浩らがボン補足協定や在伊米軍基地使用の実態に関する実務取り決めなど訳出し、紹介してきた。また、伊勢﨑賢治と布施祐仁は、独・伊両国に加え、韓国・フィリピン・アフガニスタン・イラクの地位協定と日米協定の徹底比較を通じて、国家が独自の意思決定を行う権利としての主権が「大きく損なわれている」日本の姿を抉りだした。
それらの業績によって、ドイツやイタリアに駐留するNATO軍(米軍を含む)を規定する取り決めと日米地位協定とでは―とりわけ受け入れ国側の基地への立ち入り、基地に対する管理権、受け入れ国法令の適用に関して―著しく異なることが判ると、琉球新報ならびに中国新聞取材班が独・伊両国に取材し、運用の面でも日本と大きく異なることを明らかにした。
◆沖縄県「他国地位協定調査」
NATO諸国における地位協定の内容と運用実態が明らかになる一方、日本政府による地位協定問題への対応は、協定自体には手をつけず日米合同委員会の合意を改訂したり新たに作成することとほぼ同義の「運用改善」に終始してきた。米軍基地を多く抱え、結果、米軍による人々の生活への被害をもっとも多く受けてきた沖縄県は、そのような対応だけでは「不十分」とし、協定の抜本的な見直しの必要性を訴え続けてきた(もっとも、近年、日米両政府は「第3の手法」として補足協定を結ぶ傾向にあるが、その実効性については疑問視する声も多い)。そして沖縄県は、地位協定見直しの必要性に対する理解を「国民全体」に広げ、国民的議論を喚起することを重視するにいたった。おりから、県議会によって他国地位協定調査の必要性が指摘され(2017年7月)、全国知事会の「米軍基地負担に関する研究会」でも日米地位協定を他国と比較した際の「相場観」を知る必要があるとの声があがっていた(2017年6月)。
こうして、2017年度より沖縄県が取り組んでいる本調査は、他国との比較論的調査という古典的な手法に依りながらも、近年の政治的要請にも応えるものと評価することができる。調査に際しては、他国においても地位協定の下に合意事項、国内法令、同法令に依拠する通達・規程が存在し、「そのすべてを詳細まで調査を行うことは難しい」こと、また米軍に起因する事件・事故など、日本と「類似の事案」は他国でも発生し、その対応の過程で「地位協定や受入国の国内法令、両国間での合意事項などが反映され」るとの認識から、各事案への各国の「対応(事例)を比較する」ことにより、日本と他国における地位協定運用の違いを「より鮮明にする」という方針が採られている。地位協定問題への国民的な議論を喚起するためには、難解で煩雑な「法令を中心にした調査」ではなく、こうした「対応(事例)」中心の調査方針を採った点に特色がある。
◆受け入れ国の基地立ち入り権と管理権
沖縄県が2017年度に行った「他国地位協定調査」から得られた大きな成果の一つは、独伊両国による米軍基地への立ち入り権が改めて確認されたことであった。
すでに本間浩の訳業により、ドイツの連邦・州・地方自治体の当局は「ドイツの利益を保護するため」に事前通告後基地へ立ち入るだけでなく、緊急時などには「事前通告なし」で立ち入ることが知られていた。さらに琉球新報や中国新聞の取材班は、立入り許可証を発行された基地所在地の首長や職員が、公務遂行のため事前通告なく「常に立入りを認められている」ことを明らかにしていた。沖縄県も、空軍基地が所在するラムシュタイン市などの当局者から、適切な理由があれば、一度に入れる人数や時間帯に制限はあるものの、「これまで市の立ち入りが認められなかったことはない」、「事前申し込みなしで基地内に立ち入ることが可能である」 との証言を得ている。
イタリアにおいては、これもまた本間の論稿によって、そもそも在伊基地は原則としてイタリア人司令官の統括権(jurisdiction)下に置かれることが知られていた。これに関して沖縄県は、元NATO空軍司令官や元首相経験者から、「アメリカが活動しようとするときは、必ずイタリア軍の司令官に伺いを立てなければならない」、あるいは「米軍はすべての活動について イタリア軍司令官の許可が必要だ」との証言を得た。このように、受け入れ国側に強い基地管理権があることから、イタリアの司令官は「その責任に対応するため」に、また「イタリア国主権の擁護者として」、基地のすべての区域および施設へ自由に立ち入ることができるとされる。前記の琉球新報取材班は、事前通告や立ち入り者の名簿提出といった手続きが必要な「機密施設」を除けば、イタリア人司令官は全施設へ無制限に立ち入れるという、日本と「全く異なる」運用実態も明らかにしている。
2018年度「他国地位協定調査」では、受け入れ国による基地への立ち入り権が独伊以外の国でも認められていることが確認された。米空軍シエーブル基地が所在するシエーブル市(ベルギー)の市長は、「私は当然、基地に入る権利があるし、入ることができる」「基地の中で何かが起きれば、私の市民たちの安全を確実にするために確かめる必要があるし、そうではない平常時であっても、基地で何が起こっているかを知る権利がある」と述べているのだ。基地提供を受けている側の基地広報官も、基地周辺自治体の「首長だけでなく、市役所の職員でも基地内には当然入ることができる」理由として、基地が「基地はベルギーの領土内にあるのだから」と証言している。
◆日本国法令の「尊重」にとどまる日米協定
また、日米地位協定が、米軍人・軍属・それらの家族による日本国法令の「尊重」義務を規定し、米軍の作業は「公共の安全に妥当な考慮を払つて」行わなければならないなどと定めるのみであることも問題だ。 この点に関する政府(外務省)の考え方も、外国の国家機関である軍隊が受け入れ国の主権の 下に服さないことの「当然の帰結」として、「一般国際法上」、外国軍隊には受け入れ国の法令の適用が「ない」のであり、したがって米軍に対しても、特定の事項に関する法令の適用が日米間で合意されている場合を除き、基地内外を問わず「原則として我が国の法令の適用はない」 という立場をとってきた。
米軍に国内法令が適用されないとどうなるか。たとえば、その第6章で粗暴な操縦の禁止(第85条)などを定める航空法は、地位協定に基づく航空特例法― だから、正確には特例法という国内法の適用による航空法からの除外ということになるのだが―によって米軍機には多くの規定が適用されない。そうした状況においても地位協定の運用改善によって対応していくことが合理的と説明する日本政府に対し、「米側に裁量を委ねる形となる運用改善だけでは不十分であり、日米地位協定を抜本的に見直すことで、米軍にも国内法を適用し、自国の主権を確立させる必要がある」というのが沖縄県としての「考え」である。沖縄県に加えて、日本弁護士連合会や野党議員も、基地周辺住民の権利侵害の多くは「日本法令の適用除外」によって起きており、「一般国際法」の根拠は如何と政府に質してきた。さらに近年では、米国政府や米軍内にさえ、外国軍隊は国際法上、受け入れ国の法律に従うべきだとの見解を示す者もいる。だが日本政府は、指摘を受け、外務省のホームページにある「日米地位協定Q&A」から具体的根拠の示せない「国際法」の文言を削ったものの、国内法令不適用の根拠が国際法にあるとする姿勢は変えていない。
日米間にこうした状況があるいっぽう、2018年度「他国地位協定調査」に応じたベルギーおよびイギリスの専門家たちは、受け入れ国国内法令適用について重要な考え方をいくつも示している。とくに私が着目した考え方は三つある。まず、「領土主権」(領域主権)である。これは、受け入れ国は自国の領域内にある全ての人と物に対して立法管轄権と法執行権を有するという考えで、「国際法の基本」である。したがって、「一般的に、特別な協定がない限り駐留軍には受入国の国内法が適用される」ことになる。日本の外務省の考え方とは正反対なのだ。(ちなみに、日弁連が政府に国内法の適用を求めるのもこの考え方に基づいており、この考えを裏づける「条約法に関するウィーン条約」には日本も1981年に加盟している。)
次いで、土地や環境といった価値とともに、何より「市民の権利」を守らなければならない、という考え方である。たとえば、ドイツで行われていたNATOの飛行訓練を1990年に受け入れることになったベルギーでは、受け入れ地住民の間に騒音への懸念が高まった。そこでベルギー政府は地元の合意を得るために国内法令改正により飛行下限高度を引き上げ、低空飛行を規制した。「他国と協議しなければならないことではない」という。「他国」より「地元の合意」を優先するベルギー政府の姿勢は、沖縄県の度重なる要請に重い腰をあげようとしない日本政府のそれとは異なる。
最後に、「軍は様々な理由で駐留しているので、国内法による規制で駐留軍が撤退してしまうようなことはベルギーではあり得ない」という考え方も示唆を与える。しばしば、日米地位協定の改定を求めれば、米国が日本やアジア太平洋地域に対する関与を減退させることにつながりかねないという議論を耳にする。しかし、まさに米軍は「様々な理由」で日本に駐留している。兵站基地としての日本は米軍から「最高点に近い評価」を得ているという。加えて、駐留経費負担の面でも日本は「非常に気前がいい」。そして近年では、集団的自衛権行使容認も閣議決定された。
このような状況を考えあわせるならば、内閣は国内法―とりわけ沖縄県の要望の強い航空法 ―を米軍にも適用して、沖縄に静かで安全な空を取り戻すことを躊躇うべきではないだろう。前年度調査で得られた「沖縄が抱える問題は、日本の政治家が動いて条約を勝ち取らないと解決が難しい。……世界の状況を見れば、米国が日本を必要としていることは明らかなのだから、そこをうまく利用して立ち回るべきだ」というランベルト・ディーニ伊元首相の言葉が想起される。その「政治家」を動かすためにも、日米地位協定問題をめぐる真の国民的議論が行われることを望む。
※以上は、2019年4月刊行の沖縄県「他国地位協定調査報告書(欧州編)」に掲載された拙稿に、2022年7月に加筆・修正を行ったものです。
明田川 融
1963年生まれ。法政大学で博士号取得。政治学。現在 法政大学教授。著書『日 米行政協定の政治史——日米地位協定研究序説』(法政大学出版局、1999)『各国 間地位協定の適用に関する比較論考察』(内外出版、2003、共著)、『沖縄基地 問題の歴史——非武の島、戦の島』(みすず書房、2008)、『日米地位協定——その 歴史と現在(いま)』(みすず書房、2017、第36回(2018年度)櫻田会奨励賞。訳書 ジョン・ハーシー『ヒロシマ 増補版』(法政大学出版局、2003、共訳)、ジョン・W・ダワー『昭和——戦争と平和の日本』(みすず書房、2010、監訳)。