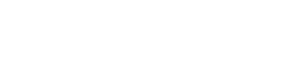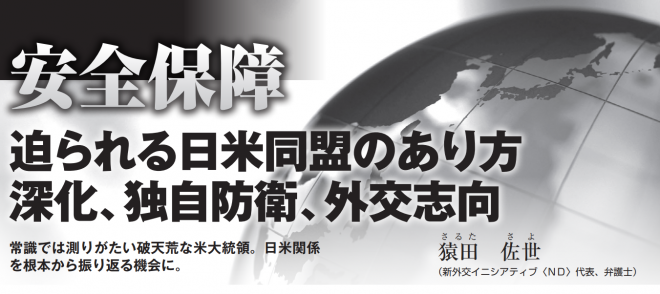常識では測りがたい破天荒な米大統領。日米関係を根本から振り返る機会に。
今年1月に米国大統領に復帰したトランプ氏が、世界を騒然とさせる発表を連発している。「(デンマーク領の)グリーンランドを手に入れる」「メキシコ湾ではなくアメリカ湾だ」など枚挙にいとまがない。2月末にウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、激しい口論となったのもその一つである。
トランプ氏は、ゼレンスキー氏に向かって「あなたは第三次世界大戦が起きるかどうかを賭けたギャンブルをしている」と批判。ゼレンスキー氏は必死に反論したが、一方的に責められる様子が世界中に報じられた。その後、トランプ氏は、ウクライナに対する軍事支援を一時停止した。
「もう米国は他国を守らない」──。欧州に大激震が走り、欧州諸国は団結してウクライナを支援すると宣言した。現在、ロシアに対抗するため、欧州自らによる防衛力強化に向けた政策変更が各国で相次いでいる。
一方、日本の石破茂首相は、このトランプ・ゼレンスキー会談の3週間前にトランプ氏を訪ね、「トランプ氏は神に選ばれたと確信」「対米投資を1兆ドルに引き上げる」などと述べ、日米同盟を一層強化するとの日米共同声明を得て、初会談を無難に乗り切ったと評価されていた。しかし、この米・ウクライナ首脳会談を経て、日本にも日米同盟に対する「米国は日本も守らないのではないか」といった不安が広がった。
米国の日本防衛義務は
その直後の3月6日、トランプ氏は、「日本はアメリカを守る義務はない。いったい誰がこんなディールを結んだのか」と述べ、日米安全保障条約の内容が不公平だと不満を口にした。NBCなどの米国メディアは3月19日、米国防総省が在日米軍強化の計画を中止する可能性があると報じた。トランプ氏は北大西洋条約機構(NATO)についても、「加盟国が自国の防衛費を十分に支払わなければ、米国は(欧州を)防衛しない」と述べている(3月6日)。
日米安全保障条約は、米国の対日防衛義務(第5条)を定めたもので、そのために日本における米軍の駐留を認める(第6条)。トランプ氏が日米安保を「タダ乗りだ」と批難し、米国が日本を防衛しないのであれば、日米安保の根幹が揺らぐ。
トランプ政権から次々発動される関税政策は、世界中の自由貿易秩序を大きく変えている。そしてその関税措置は同盟国に対しても容赦なく、日本も主要なターゲットとなっている。
アメリカ革命 2025特集35 週刊エコノミスト 2025.5.6トランプ政権が掲げる米国第一主義は2期目に突入して濃度を増している。日本においても、米国との関係について改めて考える機会が来たといえるだろう。今年は戦後80年の節目でもある。
対米従属深めるリスク

選択肢は三つある(図)。現状維持である日米同盟を強化する方向(A)と、程度の差はあれ米国離れする方向(B)だ。そして、(B)のうち、米国離れした上で日本独自の防衛力の大幅強化か(B1)、日米安保から離れつつ防衛力は現状維持として外交努力に注力(B2)するか、である。
日本政府、また、外交・安保政策関係者の大半は(A)を志向するだろう。懸命に米国にしがみつく結果、多くを搾り取られることになる。現在、米国からは、日本に対して、防衛費を国内総生産(GDP)比3%まで引き上げるよう求める声が上がっているが、トランプ氏に見捨てられないためにも、それも受け入れる方向で検討する可能性が高い。日本政府は2027年度に防衛費をGDP比2%にまで増やすことを決定しているが、3%への引き上げならさらに約6兆円が必要となり、例えば、消費税であれば税率12%程度としなければならない。
もっとも、国民がインフレに苦しむ中、消費税を含め各種税率引き上げは政治的に容易でなく、「防衛国債」の発行の声も上がるが、それも既に悪化した日本の財政状況をさらに悪化させた上で問題を先送りするだけである。
また、トランプ政権下での(A)の選択は、日本の国際的な評価を低下させるなど多くのリスクもはらんでいる。最近来日した米国人の外交研究者は次のように指摘していた。「日本が対米関係を現状のまま維持するならば、民主主義、人権、法の支配などを推進してきた従来の『国際秩序』を壊し続ける米国に付き従う国というメッセージを世界に発信する。また、日本がロシアや中国などの強権的な陣営に半分くらい足を突っ込むことも意味する」
さらには、そのようなリスクを甘受して日米同盟の深化を図っても、いざという時にトランプ政権が日本を守ってくれない可能性も高いのである。
選択肢(B)はどうか。(B1)と(B2)では政治的支持層は二つに分かれるだろう。(B1)を選択するのはおおむね保守派・右派である。日本が独自に防衛力を高めて、必要ならば核兵器保有も排除しない。もっとも、核武装を日本政府が本気で掲げれば、また、核に限らず、大幅な防衛力拡大は、前述の通り、財政的にも相当困難で、実現は見通せない。他国もこぞって核武装を始めると思われ、NPT(核拡散防止条約)体制は崩壊し、日本の安全向上のための選択肢とは言い難い。
リベラル・左派層は(B2)を志向するだろう。この層は、日本が戦争に巻き込まれることを恐れ、緊張緩和のための外交努力が必要だと訴えている。ただ、「中国、北朝鮮、ロシアは怖いし、果たして可能なのか」という世論の反応も少なくない。現状を見る限り、支持者は三つの選択肢の中で最も少ないかもしれない。
いずれの選択肢を取ったとしても、外交による緊張緩和は決定的に重要なのだが、「外交を!」と声を上げることがはばかられるような空気感が漂っている。
世界では軍事化が著しい。英シンクタンクの国際戦略研究所(IISS)によると24年の世界合計の防衛費は前年比7.4%増の2兆4600億㌦(約377兆円)と過去最高を記録した。とはいえ、軍事力強化のみでは平和は訪れない。これから安保政策見直しの議論が加速するだろうが、軍拡を進めて戦争に突入していった歴史の教訓を忘れてはならない。