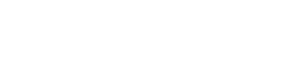「移設先となる本土の理解を得られないなどさまざまな事情で、目に見える成果が出なかった」
2018年2月2日の衆議院予算委員会で、安倍晋三首相は沖縄の米軍基地負担軽減についてこう答弁した。在日米軍基地の75%が集中する沖縄の負担軽減が進まないことの真相がそこにある。自分のところでは嫌だから押し付けているだけ。
首相答弁に対し翁長雄志沖縄県知事は、「県民をないがしろにする理不尽なものだ」と不快感を露わにする。昨年(17年)暮れにヘリコプターの窓枠が落下した普天間第二小学校では、以来、怖くて校庭を使えず、グラウンドから子供たちの笑い声が消えた。それでも、沖縄で良かった、という意識が日本人の心の奥底に宿ってはいないだろうか。
「戦争に負けたから仕方ない」とか、「沖縄は対中国抑止で米軍基地を受け入れるべきだ」といった言説に多くの日本人はうなずき、無関心でいられる。同小学校には「基地ができた後に学校を建てたのだから文句を言うな」「沖縄は基地で食っているだろう」といった暴言が本土側から投げつけられた。毎日新聞はそれを「米軍ヘリ窓落下 被害小学校、続く中傷 のぞく沖縄差別」(2017年12月25日付朝刊)と報じた。
基地問題に横たわる差別。日本人の沖縄に対する仕打ちは戦前戦後、そして現在も一貫して続いている。
「玉砕」と「千秋楽」
沖縄戦末期の1945年6月、沖縄根拠地隊司令官だった大田實海軍中将は那覇市の隣にある豊見城市(とみぐすくし)の海軍壕で海軍次官宛てに電報を打った。瀕死の状況を大本営海軍次官に報告した。(以下、著者現代語訳。電報の原文は防衛研究所所蔵の「南西諸島方面電報綴(昭和20.6)」)
「青壮年は全員防衛召集に応じ、残る老幼婦女子は砲弾の中を彷徨し、風雨にさらされながらとりあえず生き延びているが、戦況の厳しさから軍は住民をかまう余裕がない」。さらに続けて、「若い女性は看護や炊事ばかりか挺身斬り込みすら申し出る者もいる」とし、軍に対する沖縄島民の献身をつづった。
また「米軍に捕まれば老人子供は殺され、婦女子は辱めを受けるだろうと、軍門に娘を置き去りにする親もいた」という。それは軍隊と行動を共にすれば守ってくれる、と信じていたためだろう。
「一木一草焦土と化せん。糧食6月一杯を支うるのみという。沖縄県民斯く戦えり。県民に対し後世特別の御高配を賜わらんことを」
6月6日の打電後、大田中将は13日に壕内で自害した。
沖縄米軍基地の始まりは住民を巻き込んだ戦争であり、沖縄戦は基地問題を考える上で不可欠な要素である。さらに大田中将が大本営に電報を打ってから自決するまでの間、東京両国国技館では大相撲夏場所が行われていた(6月7~13日の7日間)という史実を知るとき、沖縄問題の実相が浮かび上がる。
東京も大空襲の被害を受けていたため、そのときの夏場所はさすがに一般興行とはいかず、傷痍軍人を招いての巡業だった。大田中将が自決した13日がちょうど千秋楽で、翌日の新聞にはその結果が報じられている。
沖縄玉砕と東京の夏場所が同時進行する時空をどう受け止めればいいのだろうか。沖縄に生まれ育ち、両親から戦争の地獄を聞いた筆者にとっては、島に犠牲を招いた為政者が住む中央とのギャップに頭がくらくらするのだ。「沖縄」は日本にとって守るべき領土、国民ではなかった。その扱いは果たして現在は変わっただろうか。
諫山(いさやま)春樹方面軍参謀長はこう語った。「結局われわれは、本土決戦のための捨て石部隊なのだ。盡(つ)くすべくを盡くして玉砕するの外はない」(吉川成美『沖縄戦秘録 死生の門』1949年)。沖縄防衛の日本軍は沖縄守備軍の8万6000人、海軍1万人、そして現地徴用のにわか兵隊2万人の計約11万6000人。対して攻める米軍は54万人だった。周辺の海が戦艦で埋められたという。兵力、戦力、物資のいずれも圧倒的に米軍が凌駕した。諫山参謀長が吐いた「われわれは結局本土決戦のための捨て石部隊なのだ」という表現通り、勝つためでもなく、守るためでもない。最後の一兵まで命を賭し、少しでも長く米軍を沖縄に足止めする任務はすべてが本土防衛のためだった。
軍門に娘を置き去りにした親たちは砲弾が降り注ぐ中を逃げ惑ったことだろう。軍に預けた愛娘の命を思いながら駆けただろう。ところが真実は残酷だ。捨て石部隊に託す一縷の望みなどはじめから叶うべくもなかった。沖縄住民も同様に時間稼ぎの捨て石に使われてしまった。
「沖縄玉砕」と「千秋楽」という二つの言葉が虚しく絡まり、沖縄の犠牲の中に溶け合っていく。
そして米軍による沖縄占領が27年間続いた。
差別を利用せよ――「民事ハンドブック」からわかること
捨て石とされた沖縄を米軍はどう見ていたのかがわかる資料がある。米海軍作戦本部が1944年11月に編纂した「琉球列島に関する民事ハンドブック(Civil Affairs Handbook Ryukyu 〈Loochoo〉 Islands)」。沖縄の歴史、地理、文化、人種、習慣、社会組織、経済などを幅広く分析している。将校らに配布され、戦後の占領政策に大いに活用された。
沖縄の「民族的立場」という項目にはこう記された。本土と沖縄の関係性に対する第三者の見方は冷静、端的で戦略性を帯びている。やや長い引用だが必見だ。
「日本人と琉球島民との密着した民族関係や近似している言語にもかかわらず、島民は日本人から民族的に平等だとはみなされていない。琉球人は、その粗野な振る舞いから、いわば『田舎から出てきた貧乏な親戚』として扱われ、いろいろな方法で差別されている。一方、島民は劣等感など全く感じておらず、むしろ島の伝統と中国との積年にわたる文化的つながりに誇りを持っている。よって、琉球人と日本人との関係に固有の性質は、潜在的な不和の種であり、この中から政治的に利用できる要素をつくることが出来るかも知れない」(『沖縄県史 資料編1』1995年、原文・和訳所収)
米軍には、本土の沖縄に対する差別は明白だった。「沖縄玉砕」と「千秋楽」が同時期に存在したことは、攻める米軍にとっては好都合だったのかもしれない。天皇を中心とした国体護持のシステムの中で最も外側の縁に沖縄があり、米軍はこの関係性を政治的に利用できる要素だと見抜いていた。
なぜなら外国軍の占領、駐留は常に政治的な圧力を受けるため、反対運動が国内問題として発火しにくい場所が基地建設に適している。日本各地で50年代から米軍基地に対する反対運動が盛り上がり、60年と70年の安保闘争へと炎上した。現在、反基地運動は沖縄の風土病のように語られるが、かつて本土でも機動隊との激しいぶつかりあいがあった。非暴力不服従の沖縄のそれはむしろおとなしいくらいだ。米軍を受け入れる韓国、ドイツ、イタリアなどでも同様に反基地闘争はある。
捨て石にされた沖縄なら、米軍の占領、基地建設を進めても日本国内で政治圧力は上がらないと見ていた。それが「民事ハンドブック」から読み取れる。差別構造の中で日本人と琉球人には対立の種があり、それを政治的に利用する。沖縄戦を前に、米軍は基地を長年存続できる仕組みを構想していたともいえる。
ダグラス・マッカーサー極東軍司令官も沖縄についてこう述べている。
「この諸島の住民は日本人とは民族的に同一ではなく、日本の経済福祉に貢献せず、しかも日本人はこの諸島の所有を認められることを期待していない」「琉球の住民は日本人ではなく、本土の日本人と同化したことがない。それに日本人は彼らを軽蔑している。彼らは単純でお人よしであり、琉球諸島におけるアメリカの基地開発により、かなりの金額を得て比較的幸せな生活を送ることになろう」(日本国際政治学会編『国際政治のなかの沖縄』所収のロバート・D・エルドリッヂ「ジョージ・F・ケナン、PPSと沖縄」より)
軍部はことさら琉球の異質性を強調し日本から切り離したがっていたことがわかる。「民事ハンドブック」の内容が軍政に色濃く反映された。マッカーサーは沖縄に空軍基地を置けば極東アジアの戦略拠点となり、日本防衛にも十分な拠点となると主張していた。
戦後、米軍は住民を強制収容所(県内12カ所)に集め、基地建設のため多くの土地を奪った。戦闘行為が終了すると徴用した財産の即時返還が国際条約で規定されているが、アメリカはそれを無視し、沖縄占領を続けた。
マッカーサーの見立ては結果的にその通りになってしまった。その洞察が優れて正確だったことは沖縄で何度も証明されている。沖縄で米軍ヘリが落ち、若い女性がレイプの後に殺害されたとしても「貧しい親戚」の不幸として扱われる。沖縄の基地問題で国会が騒ぎになることもないし、本土側で一部に基地の負担を分かち合おうという声はあるがほとんど広がらない。
筆者の母親は戦時中まだ10代で、熊本県へ疎開し、終戦を迎えた。その夏、ちょうど山鹿灯籠の時期で、夕闇に灯籠が揺れた。終戦とともに本土では祭りが復活し、平和を実感できた。しかし疎開先で母は沖縄に残した両親らの安否がわからず、ぼんやりと灯籠を眺めるしかなかった。
本土では戦後復興、高度経済成長へと邁進する。他方沖縄は講和条約で本土から切り離され、日本独立の引き換えに米軍に質入れされた。さらに50年代に本土から追い出された海兵隊が移転し、現在の普天間問題へと続いている。
基地を沖縄に置きたがるのは日本政府
沖縄に対する“占領者の眼”は昔もいまも変わっていない。それがわかる資料が最近発掘された。米海兵隊のオリエンテーション資料で、本国基地からローテーションで沖縄に派遣される隊員に、沖縄の歴史や文化、生活の注意点などを教えるために作成された。
オリエンテーションのスライドデータなどがイギリス人ジャーナリスト、ジョン・ミッチェル氏の情報公開請求で明らかになった。その中で「沖縄の歴史と政治情勢」のタイトルが付いた資料がある。「沖縄の歴史を学び、日本、米国との関係を理解する」ことによって、「海兵隊と沖縄のより良い関係を見出す」ことを目的に作成された。歴史パートでは12世紀に始まる琉球王朝から、薩摩侵攻、琉球処分、沖縄戦、戦後の米軍支配、本土復帰とその後の経済振興までを一通り概説している。
注目したいのが、「日本本土との関係性」に関する記述だ。「沖縄の住民は多くが日本人よりも沖縄人を自認し、愛国的な日本人だと認識する人々は少ない」と沖縄人の独自性を説明。そして日本と沖縄の関係性について、「沖縄は1879年に日本に組み込まれて以来、差別を受けてきた。日本人は沖縄のことを遅れた非日本人とみなしている」と書いた。1944年作成の「民事ハンドブック」が米軍の中でまだ沖縄駐留の下敷きになっているかのような認識だ。
沖縄の基地集中について実に興味深い記述があった。
「日本政府と沖縄県は長年基地をめぐり対立している。政府は米軍基地と部隊を沖縄に置きたがっている(なぜなら本土に代替地を探せないからだ)。日本政府は米軍兵士による事件事故、歴史的な基地の集中を理由に沖縄の負担軽減を求めている」
この文章から、米軍基地を沖縄にとどめ置きたいのは日本政府であって、米軍ではないという事実が明らかになる。例えば海兵隊の移転先を九州などで用意できれば、部隊は移転可能なのだが、日本人はそれを拒絶する。2012年の米軍再編で海兵隊は1500人を沖縄から山口県岩国基地へ移転させようと日本政府に提案したが、当時の民主党・野田佳彦政権は拒否した。そのような事例は過去にいくつもある。
冒頭に紹介した安倍首相の答弁の通りだ。安倍政権も普天間飛行場に配備されたオスプレイなどの飛行訓練を佐賀空港に分散移転する方針だったが、地元の反対でその計画は雲散霧消した。政府は沖縄で反対の声をあげても辺野古埋め立てをゴリ押しするが、山口県や佐賀県の反対はなぜ許されるのか。
野田政権で民間初の防衛大臣となった森本敏(さとし)氏は、離任会見で沖縄の海兵隊についてこう語っている。
「(海兵隊の駐留地は)日本の西半分のどこかに、その3つの機能(陸戦部隊・航空・後方支援)を持っているMAGTF(海兵空陸機動部隊)が完全に機能するような状態であれば、沖縄でなくても良いということだと。これは軍事的に言えばそうなる」(2012年12月25日)
政府は従来、海兵隊の沖縄駐留は変更不可能な地理的優位性に基づく、と繰り返し説明してきた。沖縄でなくてもいい、という防衛大臣の発言は長年基地問題を取材してきた筆者にとって衝撃的な真実の暴露だった。
しかし森本大臣は現状を追認する理由をこう説明した。日本に「政治的な許容力、許容できる地域」がない。「政治的に許容できるところが沖縄にしかない」とした上で、「軍事的には沖縄でなくても良いが、政治的に考えると、沖縄がつまり最適の地域である」と語った。(同上)
言葉を変えれば、みんな嫌がっているから、日本人が許容できる沖縄を生贄に差し出そう、ということか。日米同盟の正体はそんなものだろうか。沖縄はいまも「捨て石」なのだから、将来再び「玉砕」の悲劇を見る運命を背負わされている。
(集英社「情報・知識&オピニオン imidas」屋良朝博「日米同盟はいかに沖縄差別を利用してきたか-戦時期から続く沖縄統治の方法」2018年2月23日)