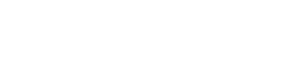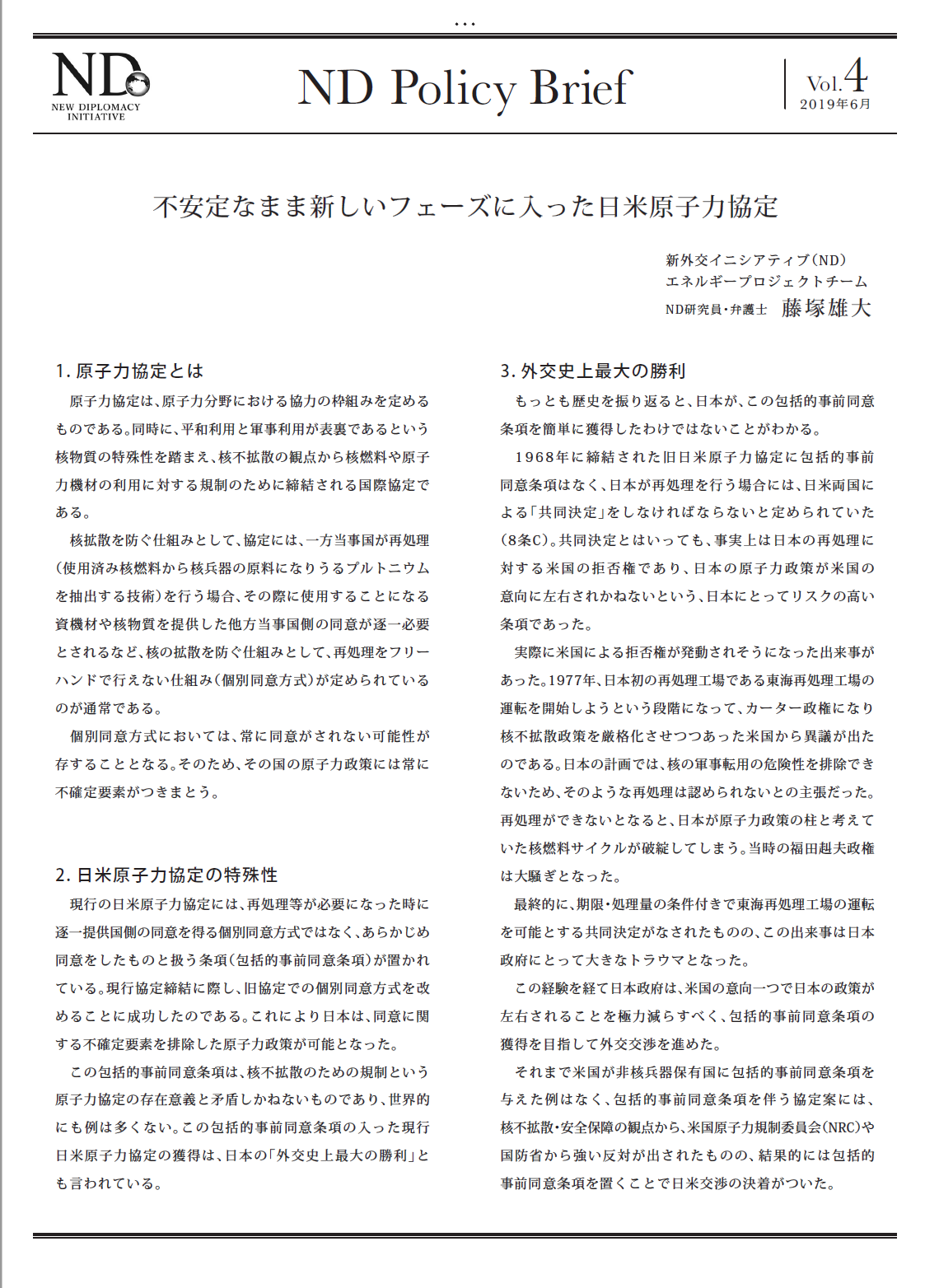不安定なまま新しいフェーズに入った日米原子力協定
1 原子力協定とは
原子力協定は、原子力分野における協力の枠組みを定めるものである。同時に、平和利用と軍事利用が表裏であるという核物質の特殊性を踏まえ、核不拡散の観点から核燃料や原子力機材の利用に対する規制のために締結される国際協定である。
核拡散を防ぐ仕組みとして、協定には、一方当事国が再処理(使用済み核燃料から核兵器の原料になりうるプルトニウムを抽出する技術)を行う場合、その際に使用することになる資機材や核物質を提供した他方当事国側の同意が逐一必要とされるなど、核の拡散を防ぐ仕組みとして、再処理をフリーハンドで行えない仕組み(個別同意方式)が定められているのが通常である。
個別同意方式においては、常に同意がされない可能性が存することとなる。そのため、その国の原子力政策には常に不確定要素がつきまとう。
2 日米原子力協定の特殊性
現行の日米原子力協定には、再処理等が必要になった時に逐一提供国側の同意を得る個別同意方式ではなく、あらかじめ同意をしたものと扱う条項(包括的事前同意条項)が置かれている。現行協定締結に際し、旧協定での個別同意方式を改めることに成功したのである。これにより日本は、同意に関する不確定要素を排除した原子力政策が可能となった。
この包括的事前同意条項は、核不拡散のための規制という原子力協定の存在意義と矛盾しかねないものであり、世界的にも例は多くない。この包括的事前同意条項の入った現行日米原子力協定の獲得は、日本の「外交史上最大の勝利」と言われている。
3 外交史上最大の勝利
もっとも歴史を振り返ると、日本が、この包括的事前同意条項を簡単に獲得したわけではないことがわかる。
1968年に締結された旧日米原子力協定に包括的事前同意条項はなく、日本が再処理を行う場合には、日米両国による「共同決定」をしなければならないと定められていた(8条C)。共同決定とはいっても、事実上は日本の再処理に対する米国の拒否権であり、日本の原子力政策が米国の意向に左右されかねないという、日本にとってリスクの高い条項であった。
実際に米国による拒否権が発動されそうになった出来事があった。1977年、日本初の再処理工場である東海再処理工場の運転を開始しようという段階になって、カーター政権になり核不拡散政策を厳格化させつつあった米国から異議が出たのである。日本の計画では、核の軍事転用の危険性を排除できないため、そのような再処理は認められないとの主張だった。再処理ができないとなると、日本が原子力政策の柱と考えていた核燃料サイクルが破綻してしまう。当時の福田赳夫政権は大騒ぎとなった。
最終的に、期限・処理量の条件付きで東海再処理工場の運転を可能とする共同決定がなされたものの、この出来事は日本政府にとって大きなトラウマとなった。
この経験を経て日本政府は、米国の意向一つで日本の政策が左右されることを極力減らすべく、包括的事前同意条項の獲得を目指して外交交渉を進めた。
それまで米国が非核兵器保有国に包括的事前同意条項を与えた例はなく、包括的事前同意条項を伴う協定案には、核不拡散・安全保障の観点から、米国原子力規制委員会(NRC)や国防省から強い反対が出されたものの、結果的には包括的事前同意条項を置くことで日米交渉の決着がついた。
その背景には、米国の東海再処理工場の一件でぎくしゃくした日米関係を米国としても修復しようという思惑があったとも言われている。
現行協定にとっての山場は米議会審議であった。米国において原子力協定が発効するために必要な要件は、米国議会において、審議対象となっている協定案に賛成しない旨の共同決議が成立せずに、継続会期中の90日間の議会審議を終了することである(1954年米国原子力法第123条)。
日米原子力協定の議会審議では、プルトニウム輸送時の安全性への懸念から反対意見が強く主張されたほか、核不拡散政策への影響の有無が大きな論点となった。
上下院の公聴会において、包括的事前同意を日本に与えることが核不拡散法上の要件を満たしていないのではないかなど、核不拡散の観点から批判的な意見が続出した。
上院外交委員会においては、協定の再交渉等を求めて米議会に再提出することを大統領に要請する書簡の発出や、協定を大統領に差し戻す旨の決議を上院本会議に提案することなどが決定されてもいる。
このように協定に反対する強い動きがあり、協定の議会通過が危ぶまれる事態もあったが、日本政府の強い働きかけもあり、協定案の成立の見込みは二転三転しながら、最終的には協定案に賛成しない旨の共同決議は成立せず協定は発効した。
この現行協定締結時の状況からもわかる通り、米国の再処理に対する核不拡散上の懸念は大変根強く、今後の日米の原子力政策の行方を考えるうえで常に意識しなければならないものである。
4 自動延長による協定自体の不安定化
現行の日米原子力協定は、1988年に30年存続するものとして締結され、2018年7月の満期における協定の行方が関係者の間で注目されていた。
原子力政策を安定的に推進したい日本政府にとっての最高のシナリオは、現行の1988年協定を相当期間延長させる条約手続きをとることであった。しかし、そのためには、米国議会審議を再びクリアせざるを得ない。
結局、現在の日米原子力協定は、米国議会委審議通過が必ずしも楽観できないこともあり、特段の手続きを行う必要のない自動延長に落ち着いた。
自動延長の場合、協定16条2項は、満期後は日米いずれか両国から六か月前の文書通告により協定を終了させることができると定めている。したがって日米原子力協定は、今後いずれか一国の判断で終了となる可能性をもつ、不安定な状況に置かれ続けることとなったのである。
5 強まる米国側の懸念
もっとも再処理を続けたい日本からは上記16条2項の通告をすることはまず考えられない。
では、日本のプルトニウム蓄積に懸念を表明し続けてきている米国からの協定終了通告はありうるのだろうか。
この点を考えるにあたって重要なのは、原子力政策をエネルギー問題の側面のみに注目して考えがちな日本とは異なり、米国では安全保障問題としてもとらえているということである。今後の行方は、米国が、現行日米原子力協定の核不拡散への影響の有無につきどう判断するかというところにかかっている。
この点、核拡散問題に対する感度が低いかに思われたトランプ政権においても、核不拡散への懸念からの日本への懐疑的視点が今なお存在することが明らかになっている。米国政府の一部高官や専門家からは、日本の再処理に対する懸念が示され、核セキュリティ上の視点のほか、北東アジア地域において日本に対する不信感が増長され再処理競争が起きれば地域の緊張が高まること、米国として他国に再処理をやめるよう説得することが困難になることなど(現に、韓国やサウジアラビアは日本並みの原子力協定を求め、米国は対応に苦慮)がその懸念理由としてあげられている。
また実際、米国議会の上院外交委員会において日米原子力協定の見直しを求める質問が行われたり(2018年2月)、米国政府が日本政府に保有プルトニウムの量の削減を求めたとの大きな報道(2018年6月10日日本経済新聞一面他)がなされたりするなどの出来事が続いている。これを受け、日本政府も保有プルトニウム量の上限を決定するなど、具体的な対応を迫られている(以上、詳細は今後のPolicy Brief参照)。
6 日本の再処理政策の再検討を
このように、米国政府の一部高官や専門家の日本の再処理に対する懸念は、日本が明確な消費サイクルを確立しないままプルトニウム保有量を増やしている現在の状況下において、現行の日米原子力協定締結当時よりも強まっていると言える。安定を求めて包括的事前同意を獲得したはずの日本政府が、不安定な自動延長とせざるを得なかったこと自体も、米国からの懸念が高まっていることを物語っているのではないだろうか。
日本政府として、米国からの懸念への対応は喫緊の課題であり、日本国内でも活発な議論が期待される。
(藤塚雄大・ふじつかたけひろ)