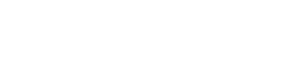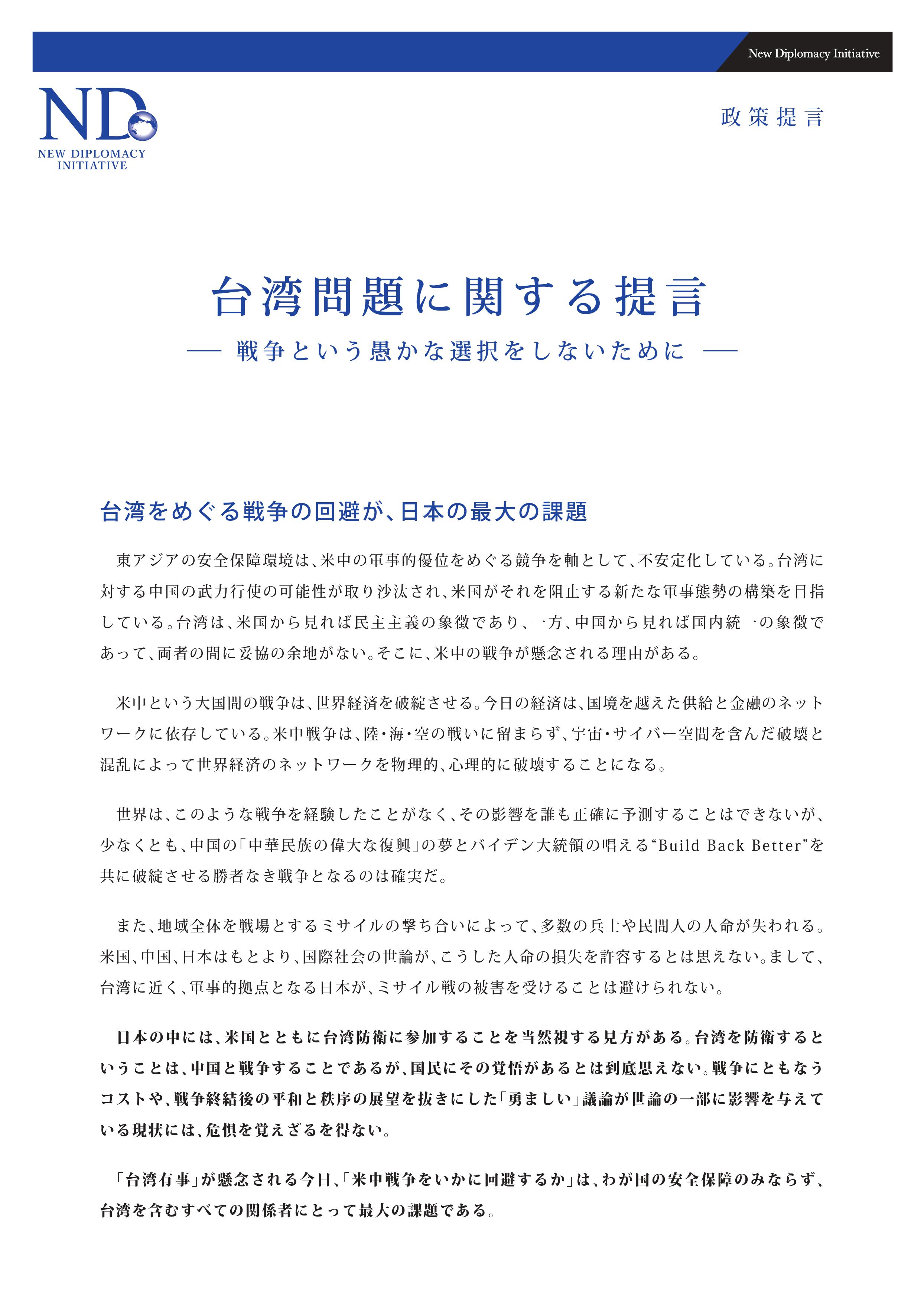PDFはこちら
■台湾をめぐる戦争の回避が、日本の最大の課題
東アジアの安全保障環境は、米中の軍事的優位をめぐる競争を軸として、不安定化している。台湾に対する中国の武力行使の可能性が取り沙汰され、米国がそれを阻止する新たな軍事態勢の構築を目指している。台湾は、米国から見れば民主主義の象徴であり、一方、中国から見れば国内統一の象徴であって、両者の間に妥協の余地がない。そこに、米中の戦争が懸念される理由がある。
米中という大国間の戦争は、世界経済を破綻させる。今日の経済は、国境を越えた供給と金融のネットワークに依存している。米中戦争は、陸・海・空の戦いに留まらず、宇宙・サイバー空間を含んだ破壊と混乱によって世界経済のネットワークを物理的、心理的に破壊することになる。
世界は、このような戦争を経験したことがなく、その影響を誰も正確に予測することはできないが、少なくとも、中国の「中華民族の偉大な復興」の夢とバイデン大統領の唱える“Build Back Better”を共に破綻させる勝者なき戦争となるのは確実だ。
また、地域全体を戦場とするミサイルの撃ち合いによって、多数の兵士や民間人の人命が失われる。米国、中国、日本はもとより、国際社会の世論が、こうした人命の損失を許容するとは思えない。まして、台湾に近く、軍事的拠点となる日本が、ミサイル戦の被害を受けることは避けられない。
日本の中には、米国とともに台湾防衛に参加することを当然視する見方がある。台湾を防衛するということは、中国と戦争することであるが、国民にその覚悟があるとは到底思えない。戦争にともなうコストや、戦争終結後の平和と秩序の展望を抜きにした「勇ましい」議論が世論の一部に影響を与えている現状には、危惧を覚えざるを得ない。
「台湾有事」が懸念される今日、「米中戦争をいかに回避するか」は、わが国の安全保障のみならず、台湾を含むすべての関係者にとって最大の課題である。
■米中戦争の危険を軽視してはならない
多くの人々は、「まさか米中が戦争することはないだろう」と考えている。戦争のコストがあまりにも大きく、勝者のいない破滅的結果をもたらす可能性があるからである。だが、不信感と敵意に満ちた国同士が、政治的・軍事的挑発を繰り返せば、いずれ、誤算や、錯誤による小さな衝突が大きな戦争に拡大する可能性があることは、歴史の教訓である。
近年、中国は台湾統一に向けた軍事力の増強と軍隊による圧力を強め、米国は、対抗措置を強めている。最近では、米国が従来の「一つの中国」政策を踏み外しかねない際どい台湾支援政策をとり、中国が挑発的な軍事行動によって不満のシグナルを発している。さらに、それを口実として米国が台湾への武器供与や軍事態勢の強化を進めるという悪循環に陥っている。
バイデン大統領は、習近平国家主席との電話会談で「競争が衝突に発展しないよう」と、ブレーキをかけるシグナルを送ったが、両者の行動に大きな変化はなく、誤算や錯誤による衝突の危険は去っていない。米中双方の政治的・軍事的自制が求められる。
日本では、こうした危険を認識すればするほど、軍事的抑止に偏った議論に終始する傾向があり、「米中に自制を求める」という視点が欠落している。
■台湾問題の平和的解決と当面の危機回避のために
「台湾問題を平和的に解決する」という目標に反対する人はいない。しかし今日、ほとんどの台湾人民が中国との統一を望んでいない現実がある。また、中国は、台湾統一の願望を変えることはなく、平和的統一が遠ざかれば遠ざかるほど、強硬な手段をとる以外の選択肢を失っていく。
両者の共存がかろうじて保たれてきたのは、米・中の政治指導者が「一つの中国」という極めてデリケートな認識によって両岸の安定を図ろうとしてきたためである。したがって、「台湾問題の平和的解決」のために必要なことは、短期的には、「一つの中国」の認識と「台湾独立の不支持」の方針を再確認することであり、中期的には、中国が武力行使以外の選択肢を持たない状況を作らないよう、関係国が慎重に行動することである。
長期的には、台湾問題をどのように解決するかは、中国と台湾自身の選択の問題である。今日の我々が思いつかない「後世の知恵」が、未来永劫出てこないと考える根拠もない。今その答えがないからこそ、戦争を回避し続けることが、関係国の政治指導者の最大の使命である。
日本は、台湾に関する「中国の立場を理解・尊重する」という1972年日中共同声明の立場を堅持し、米中双方に自制を求めるとともに、「世界を破滅させるような戦争を避けなければならない」という日本の立場を訴え続けなければならない。
■抑止(deterrence)とともに「安心供与(reassurance)」を
戦争を企図する相手に対し、戦争の目的に見合わない損害を与える能力と意思を認識させることが抑止の論理である。中国が、「台湾独立は共産党支配の核心的利益を損ない、いかなる犠牲を払っても許容できない」と考えるなら、軍事的優位だけで中国を抑止することは困難である。そこには、相手が「武力に訴えなくても核心的利益が脅かされない」と考える余地を残しておくこと、すなわち、安心供与が不可欠となる。
台湾をめぐる対立においては、「台湾の独立を支持しない」という1970年代からの政治的意思の表明が、中国に対する安心供与となる。
抑止の目的は、中国の武力行使を思いとどまらせることにある。問題の起源は、台湾側に独立をめざす底流があり、それに対し中国が不断に軍備を増強し、その行使を否定しない姿勢をとっていることにある。その一方で米国は、台湾との政治的関係を強化して、徐々に事実上の独立国として扱う「政治的現状変更」を試みている。これが中国を刺激し、更なる軍拡に走らせる悪循環が起きている。抑止を際限のないエスカレーションにしないためには安心供与の組み合わせが不可欠である。
また、日本が進んで従来の台湾との政治的関係を変更するような行動をとることは、安心供与に逆行し、抑止を不安定化させる要因となる。
■米国の抑止戦略と日本
バイデン政権のもとで、対中抑止のための作戦構想と軍事態勢の検討が進められている。米国は、中国による台湾本島占領の阻止に焦点を当てている。すなわち、中国が台湾を占領するには、台湾海峡を渡って数十万の部隊を上陸させる必要があるので、中国の艦艇を巡航ミサイルや潜水艦で殲滅するという戦い方である。これは、中国大陸への懲罰的攻撃ではなく、侵攻兵力を阻止するという「拒否的抑止」に重点を置くことを意味している。
同時に米国は、米軍に対する脅威となる中国本土のミサイル施設を破壊する中距離弾道ミサイルを開発している。このミサイルの配備に関する米国の方針は未定であるが、その射程や目的から見て、日本本土を含む第一列島線への配備が有力な選択肢となる。その場合、米中の軍事的対峙は、中距離弾道ミサイルの優劣を日本列島を舞台として競う軍拡競争となり、錯誤や誤算によるミサイル戦争の危険性を一層高めることになる。
日米両国は、抑止の目的を中国による台湾占領および日本の領域に侵攻する兵力の阻止、言い換えれば「専守防衛的な拒否的抑止」に限定すべきであり、中国本土のミサイル施設を無力化するような先制的・懲罰的な要素を加えるべきではない。日本への弾道ミサイルの配備並びに日本の敵基地攻撃能力の保有は、断じてやめるべきである。
同時に日本は、米中間の政治的誤算を避けるための対話と錯誤による衝突を防ぐための共有された危機管理の仕組みを作るよう、強く促していくべきである。
■「専制主義対民主主義の競争」という思考の罠
米バイデン政権は、中国との関係を「専制主義と民主主義の競争」と定義し、同盟国の結束を呼び掛けている。同時に、新たな感染症や気候変動といった世界的な課題における協力を呼び掛けている。だが、二国間のあらゆる分野で対立を続けながら世界的課題について協力する関係を築くことは、容易ではない。
「専制主義との競争」という単純化した対立構造で物事を見るならば、地球規模の課題から目をそらすことになりがちである。また、自己の利益のために相手に損失を与えるゼロサム的な対立に明け暮れるならば、米国であろうと中国であろうと、信頼され、尊敬される大国にはなり得ない。
日本は、米国主導の「価値観をめぐる競争」に加わるのではなく、世界的課題に対する国際協力こそが優先課題であるという立場から、米中双方に対し、身勝手な主張を繰り返すことはその国のためにならないことを、友人・隣人として、息長く説得する努力を怠ってはならない。
日本は、米国との首脳会談だけでなく、延期されている中国との首脳会談を早急に実現すべきである。大きな相違点を抱え、具体的成果が望めない状況であるからこそ、リーダーの定期対話と安全保障問題を含むさまざまなレベルの意思疎通そのものが求められている。
2021年10月
柳澤協二
(ND評議員/元内閣官房副長官補)
マイク・モチヅキ
(ND評議員/米ジョージ・ワシントン大学准教授)
岡田充
(共同通信社客員論説委員)
半田滋
(防衛ジャーナリスト/元東京新聞論説兼編集委員)
津上俊哉
(現代中国研究家)
猿田佐世
(ND代表/弁護士(日本・ニューヨーク州))
新外交イニシアティブ(ND)東アジア安全保障プロジェクト
東アジアを取り巻く包括的な安全保障について調査・研究・提言を行っています。
日本の外交・防衛政策全般に対する具体的な提言は、政策提言「抑止一辺倒を越えて―時代の転換点における日本の安全保障戦略」(2021年3月発表)をご覧ください。